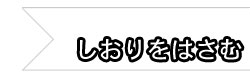下河内村(近世)

江戸期~明治22年の村名。安芸国佐伯郡(もと佐西郡)のうち。広島藩領。蔵入地と給知が入り交じる。もと河内と称したが,のちに上河内・下河内・上小深川・下小深川の4か村に分村して成立したという(芸藩通志)。分村の時期は不詳であるが,当村の「国郡志書出帳」によれば,慶長6年の検地で分村して成立したと考えられる。村高は,慶長6年検地,元和5年「知行帳」,「芸藩通志」「天保郷帳」「旧高旧領」ともに326石余。戸数・人数は,宝暦元年下河内村万指出帳74(本家60・貸家14)・370,「国郡志書出帳」133・391,安政6年組合十六ケ村諸事書出帳114・510。「国郡志書出帳」によれば,慶長6年検地では畝数28町7反余,村の広さは東西36町・南北15町,白河・木和田・大杉の飛郷があり,八幡川と荒谷川によって用水には恵まれたが時に水難を被り,生業は4割が農業,6割が山稼ぎ・駄賃稼ぎに従事,耕地は8割が稲作,2割が畑作,作物は米・麦を主とし,牛35・馬27,農間に男子は藁製品を売り歩き,女子は木綿織延べを行い,小物成として鍛冶炭札銀(18匁)・黒炭札銀(23匁)・茶銀(27.9匁)・受山銀(60匁)・いろり銀(44匁)・割木札銀(26.5匁)などを上納,飛郷白河は半紙を漉き,名産の蕨は美味なことから河内蕨と呼ばれ広島城下へ出荷された。神社は氏神山王権現,寺はなく,廃寺に地福院・長専院があった。当村の紙漉7人(国郡志佐伯郡辻)。飛郷大杉は,むかし行基が極楽寺(現廿日市市)の本尊千手観音を刻んだ大杉のあった地との伝説がある。村内を石州往還が通る。寛政9年岡岷山が著した「都志見往来日記」には,「寺田を過下河内へ移る所,川端に茶屋三軒あり,川にちさき梁あり,此所より山に登る」と記し,河内峠の図を載せている。助郷は,天保6年に山陽道廿日市宿へ人足194人,玖波宿へ189人が徴発されている(郡用諸事控/和田家文書)。明和8年に洪水の犠牲者を供養するため千蔵地蔵を建てた。安永7年から利松村と山論が起こり,文政11年に和解した。殿畑の地には「文政七年六月廿八日 此所高壱斗壱升七合 流ニ付升高否不事」と記した免租の碑がある。天保7年の飢饉で飛郷大杉では7割が青米となり,作米は僅かに2俵であったという(河内村誌)。同10年頃から河内神楽が始まり,安政5年頃小五郎なる者が盆踊りを考案した。幕末に遠藤家が私塾を開き,村内の子弟の教育にあたった。明治4年広島県に所属。この時県内に起こった武一騒動の影響で,村内でも騒動が起こった。翌5年の戸数119・人口493。同7年に小学校変応舎が開校,生徒数は男48・女7(文部省第2年報),のちに下河内小学校となり,同15年上河内小学校と合併。同21年の戸数116・人口586。同22年河内村の大字となる。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7422204 |