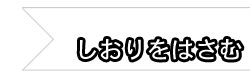小笠原
【おがさはら】

旧国名:甲斐
甲府盆地西部,御勅使(みだい)川扇状地のほぼ扇央に位置し,釜無川の支流滝沢川に沿う。市之瀬台地などの「根方」,釜無川の氾濫原などの水田地帯の「田方」に対し,当地周辺の御勅使川扇央の畑作地帯を「原方」と呼び,御勅使川扇央の旱魃地帯の7か村「原七郷」の1つである。地名の由来は,この地方が荒廃した原でスゲが多く生えており,スゲは小笠を作る材料であることから小笠原と呼んだとも,あるいは荒廃した原で小竹立原といったのを竹と立がいっしょになって笠となったともいわれる(櫛形町誌)。甲斐源氏の勇である小笠原長清は鎌倉期に小笠原荘に拠って勢力を扶植し,この地の惣領職を伝領していった。当地は天正10年織田・徳川軍の侵攻によって灰燼に帰した。地内には北町屋・西町屋・東町屋の地名があったといわれる(小笠原旧事記)。
【小笠原(中世)】 戦国期に見える地名。
【小笠原村(近世)】 江戸期~明治8年の村名。
【小笠原町(近代)】 昭和11~29年の中巨摩郡の自治体名。
【小笠原(近代)】 明治後期・大正期~現在の大字名。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典」 JLogosID : 7096331 |