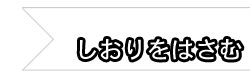大須浜(近世)

江戸期~明治22年の村名。大須ともいう。桃生郡南方【みなみかた】代官区二十四村のうち。十五浜【じゆうごはま】の中の1漁村。近代捕鯨法が輸入されるまで藩内の捕鯨根拠地だった(宮城県史)。寛永18年の村高1石余(同前)。刈田【かつた】郡白石【しろいし】片倉家の采地があった(伊達世臣家譜)。宝暦6年漁民49名が海難で溺死,明治5年49名の法名を刻んだ一墓【いちはか】供養碑を建て13回忌の供養とした(宮城県史)。明和年間の戸口は49,八幡宮と舟隠明神社があり,滝不動と聖徳太子堂があった(封内風土記)。嘉永3年には神明宮・稲荷社・地蔵尊が加わっており,大性院という修験の名も見える(安永風土記)。同年の人頭は54。天保飢饉前と変わらないのは,4代目阿部源左衛門の救恤によるという(雄勝町史)。源左衛門寿和は天保10年,鯨漁御取開の儀を仰せつけられてから「鯨漁方大主立」として藩内捕鯨漁を独占(同前),同年春まず6頭を捕獲,ほかに「余浜へ銛付候」て漂着した鯨が3頭あったという(雄勝町阿部家文書/雄勝町史)。安政6年には鯨蝋の製造方を願い出ている(本県水産資料の古記録/宮城県民新聞昭26.6.21)。同人は廻船業も兼ね,神和丸等の千石船を江戸~松前間に就航させて海産物を交易,巨富を得たという。天保年間の飢饉には酒田・水戸・秋田などの米穀を買い入れて各浜に施し,荒れ地数町を開拓させて良田とするなど窮民の救済に努めた(仙台人名大辞典)。村民は天保8年「村内一統規定の事」として,阿部家に対し「冥加の人頭一人に付一ケ年半切づつ,子孫永々其時の肝煎方にて御年貢同様に取立差上申べく候」と申し出た(雄勝町阿部家文書/雄勝町史)。天保5年の村高は24石余で,新田分は22石余である(天保郷帳)。嘉永3年の村高も24石余。村民は船59隻を所有し,アワビ・フノリ・ノリ・タラ・ホソメを主産業としていた。村内にタラの仕込みをする藩役人がいて「鱈の御仕込所」があったという(明治22年宮城県農商課調査)。御林が4か銘16万坪余あり,横峰【よこみね】に唐船番所が設置されていた(安永風土記)。嘉永4年から慶応2年,阿部家は累代が納経行脚を行い,その回数399。北は閉伊【へい】郡山田(岩手県)の法性院,南は讃岐【さぬき】(香川県)の金毘羅大権現まで総寺社数232。納経数は大般若経はじめ34種4,143巻,寄進仏像12像18体にのぼった(雄勝町史)。大須浜はまた塩竈神社神官で国学者藤塚式部知明の生誕地である。明治元年高崎藩取締地,以後,桃生県・石巻県・登米【とめ】県・仙台県を経て,同5年宮城県に所属。同3年の村高は24石余(陸前国牡鹿郡桃生郡本吉郡郷村高帳/石巻市図書館蔵)。同6年頃の戸数58,男216・女209。50石未満の船50隻を所有していた(雄勝町史)。同21年の戸数59・人口485。同22年桃生郡十五浜村の大字となる。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7255608 |