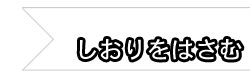藤内遺跡
【とうないいせき】

諏訪郡富士見町落合字烏帽子の藤内に所在する縄文中期の集落跡と大祭祀場。中期中葉の藤内式土器の標式遺跡である。切掛川西岸の八ケ岳南麓に特有な北から南に緩やかに傾斜する長大な尾根上で,その幅も広く当地方における縄文中期の典型的な立地である。標高は950m前後。JR中央本線信濃境駅の西方約600mに位置する。戦後の開拓地で,開拓者の1人小平辰夫が注目し,昭和28年11月(第1次)に竪穴住居跡2軒,同29年3月(第2次)に竪穴住居跡6軒,同36年8月(第3次)に竪穴住居跡1軒を発掘調査した。同年9月には水道管埋設工事で竪穴住居跡5軒と特殊遺構を確認し,井戸尻遺跡保存会は翌37年3月(第4次)に特殊遺構の一部を,6月(第5次)に竪穴住居跡1軒を発掘調査した。出土した土器と石器は優品の上に膨大である。9号住居跡は火災により廃絶した竪穴で,出土した土器は当時の生活を知る上で,また,炭化材や炭化した栗の実(約20ℓ)は家屋構造および食料品研究上の好資料である。14号住居跡の区画文土器と六段縊れの深鉢,特殊遺構の「踊る人」の描かれた有孔鍔付土器,16号住居跡の蛇体頭髪土偶は著名である。特殊遺構発見土器は大きい上に素晴らしいものばかりで,石皿や盤状の石を蓋のようにのせた例があることから,墓葬跡と考えられている。富士見町教育委員会で昭和59年11~12月(第6次)に実施した発掘調査で,竪穴住居跡10軒と特殊遺構の一部を調査した。集落の復原を試みると,遺跡は大きく分けて3つの遺構から構成されているようで,同心円状に配置している。中心に径20m位の広場があり,これをとり囲むように幅20m位の墓域(特殊遺構),さらに墓域に重なって外側に住居域のある環状集落である。三者は互いに相接し,世代や時代が変わってもそれぞれの領域を侵犯することなく,墓は墓,住居は住居として一定の決まりに基づいて営まれていたようである。なお,発掘調査はその一部が対象となったにすぎず,相当大規模な集落跡が埋没しているものと思われる。出土遺物は井戸尻考古館と尖石考古館(茅野(ちの)市)で保管・展示している。報告書には,「井戸尻 長野県富士見町における中期縄文時代遺跡群の研究」がある。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典」 JLogosID : 7102036 |