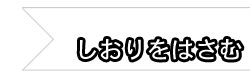呂久の渡し
【ろくのわたし】

六ノ渡りともいった(信長記)。揖斐(いび)川中流にあった渡し。中山道美江寺宿と赤坂宿との間にあって,本巣郡巣南(すなみ)町呂久と安八(あんぱち)郡神戸(ごうど)町柳原とを結んでいた。揖斐川と藪(やぶ)川との合流点のすぐ下流にあり,「岐蘇路記」に「合渡川より小なりといへども,水深くして川の流れ早く」とある。大正14年の改修工事以前の揖斐川は呂久村の西側を南流しており,元の渡船場には現在,和宮御降嫁の際の歌碑の建つ小簾紅園がある。渡しの川幅は平水で50間(約90m),中水で70間(約130m),大水では100間(約180m)に及び,4合5勺で馬越留め,5合ほどで歩行留めとなった。天正8年織田信忠がここに渡船を設け,呂久村の諸役を一切免除した。慶長7年の船賃定によると,荷物1駄につき永楽銭3文,乗懸け同2文,れんちゃく商人同1文と定め,川が増水のときもこの船賃で渡すべきこととしている。明治維新まで呂久村馬淵家が代々船年寄を勤め,苗字帯刀を許され,年ごとに扶持2人分・段木2間宛を受けて渡船に関する一切を取り仕切っていた。船夫は常務8人・助務7人であった。明治以後は呂久村地持の者で協議の上,渡船を維持した。現在はかつての揖斐川および現在の揖斐川のいずれにも橋が架けられ,渡船はない。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典」 JLogosID : 7109329 |