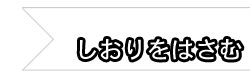小沢見
【こぞみ】

旧国名:因幡
「こぞうみ」とも称した。湖山砂丘の西,日本海に面した谷あいに位置する。東と西は,低山丘陵に囲まれ,北は小湾状をなし,西は潟湖の名残を残す湿地帯。地名の由来は,南西の奥沢見(大沢見)に対して,地内に潟湖の水尻(みずしり)池があることにちなむという(因伯地名考)。東の峠は「杖突き坂」と呼ぶ。その名は,古く弘法大師が巡錫の際,この峠の茶屋で水を求めたところ,主が数町離れた所から冷たい清水を汲んで差し出したため,峠付近が水の乏しいことを知った大師は,主への礼に杖を突き立て清水を湧かせ,茶店や旅人の難儀を救ったという故事にちなむという。また,杖なしでは越えられぬ坂の意ともいう。西の峠は「中の坂」といい,付近の半島山上に大崎城址がある。天正9年鳥取城を攻略した羽柴秀吉が伯耆(ほうき)に進出した際に毛利方であった地侍樋土佐右衛門は寡兵をもって籠城したが,秀吉は義士なりと攻撃を加えなかった。のちに佐右衛門は鳥取城主となった宮部善祥坊を頼んで秀吉に詑びを入れ,領地1,000石と城は安堵され,宮部氏の寄騎にされたが,慶長5年関ケ原の戦で宮部氏は没落,これに従った樋土氏も禄を離れて帰農した。現在懸樋の名をもつ家は,その末裔という(末恒村誌・稲葉民談記)。陣場山に古墳2~3基がある。古くから,民俗芸能に「はねそ」「どうねん」などの手踊りが盛んで,近世期旧盆には近隣の村々との間で当番日を定めて集まり,踊大会を開いた。青年相撲も行われ,近代まで続いた(末恒村誌)。
【小沢見村(近世)】 江戸期~明治22年の村名。
【小沢見(近代)】 明治22年~現在の大字名。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典」 JLogosID : 7175288 |