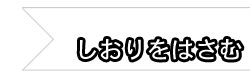小牛田町(近世)

江戸期の宿場名。遠田【とおだ】郡南小牛田村のうち。「安永風土記」は小牛田町として本町と新町の2つをあげている。同じ「代数之ある御百姓書出」によると,同村の11代相続の伊藤家6代目庄兵衛の項に「寛文二年小牛田町割仰渡され,当村の内本屋敷と申す所より取移」ったとある。同家は歴代肝煎,6代目から9代目勘兵衛までは宿駅検断も兼ね,さらに買米蔵の蔵守と塩問屋も勤めたという。江合川水運による物資集散の便があり,寛永年間には本屋敷に藩の本石蔵(年貢米集積の蔵)と塩蔵が建てられた。承応年中,本石蔵は隣接牛飼村へ,塩蔵は桃生【ものう】郡鹿又へ移転,その後町割り,同時に買米蔵も建てられたという。寛文2年に開かれた宿駅小牛田町は,石巻と鳴子【なるご】のほぼ中間,両所へ約1日の行程にあり,明治初年の旅宿営業10軒,人馬の継立や宿泊で繁盛した(小牛田町史)。石巻街道を往来する人や荷物のための伝馬用に,南小牛田村には馬60匹があった。伝馬諸役の代償として諸役免除や市開設の恩典があり,1と6の日に月6回六斎市が開かれた。町には五十集【いさば】(海産物)の荷受問屋や穀物問屋なども多く,田尻の宿駅との間で荷の奪い合いなどの紛争もあった(同前)。石巻線や陸羽東線の開通で,物資集散地としての特性を失い,以後衰えた。当地の門田家は元禄期から米穀問屋として活躍し,涌谷【わくや】伊達氏の保護などもあって,江戸への米穀輸送・販売も手がけた。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7256274 |