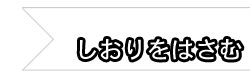福光町(近代)

明治22年~現在の町名。明治22年4月,町村制が実施されるや,福光村に荒木村の一部を編入して福光町が成立。昭和27年5月,福光町と石黒・広瀬・広瀬館【ひろせたち】・西太美【にしふとみ】・太美山【ふとみやま】・東太美・吉江・北山田・山田の9か村が合併して,現行の福光町が成立し,従来の自治体名の福光町が廃された。大字はほぼ合併町村の大字を継承。なお,明治期から大正期にかけての主要産業は生糸生産であった。明治8年,維新政府の殖産興業政策にしたがって輸出生糸の生産を高め,県下最初の機械製糸工場が創立された。さらに機械の動力源として,県下に先がけて水力・蒸気力を採用して生産増強を図ったことは特記さるべきである。県下屈指の先進的生産地であったが,昭和期に入ってから,糸価の暴落のために不況となり,第2次大戦中に廃業。大正期からは,木工業と織物業が発展して,主要産業となってきた。昭和31年大字細木・大窪【おおくぼ】・雁巻島の一部を城端【じようはな】町に分離,現在に至る。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7321512 |