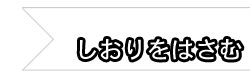藤津郡

明治11年郡区町村編制法によって改めて発足。明治11年の町村数は27村,反別6,989町・地租7万2,639円・戸数1万2,440・人口5万7,116(県史下)。郡役所は高津原村に置かれ,初代郡長は久布白繁雄。明治21年の県統計書によると,戸数1万2,068戸・人口6万4,825人(平民5万7,204人・士族7,621人)。明治23年第1回総選挙における有権者数は650人であった。同22・23年の統計書によれば,田畑小作地率は田が自作地2,484町・小作地1,427町(36.5%),畑が自作地2,122町・小作地1,110町(34.3%)となっており,専業によるもの6,239町,兼業によるもの3,651町で専業率63.1%と県下では低い方であった。商業戸数の内訳をみると,明治31年の統計書では,総戸数1万2,391戸のうち問屋9・仲売27・卸売35・小売946・雑商1,185。明治43年の牛馬の数は,牛1,583頭,馬1,587頭とほぼ同数であり,耕地が山間部と平野部とに半ばしていたことが推察できる。大正期の工業生産額の推移をみると,大正元年140万2,000円,同6年221万9,000円,同7年407万6,000円,同8年591万3,000円,同9年462万円,同10年405万4,000円となっている。この地方の物産は,米麦・水産物のほかに,茶と陶磁器があげられる。嬉野茶は不動山麓を中心に産し,江戸初期にはじまる。明治29年5月から茶業連合会議所が設けられ,製茶伝習所において研究がすすめられた。陶磁器については,志田東山・西山・塩田津・美野・久保山・吉田・内野山が有名であるが,なかでも内野山焼は江戸初期に始まり,明治になって富永源六の研究が加えられ,一名源六焼ともいわれた。大正10年4月12日,郡制は廃止となり,同15年7月1日をもって郡役所も廃止された。これによって行政区画としての郡は廃止となったが,地域名称としては存続した。昭和29年鹿島市が成立して当郡より分離。肥前山口駅から鹿島を経て諫早に至る国鉄長崎本線は,昭和5年に肥前山口~肥前浜間,昭和9年に諫早まで開通をみた。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7446578 |