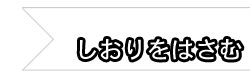竹田村(近世)

江戸期~明治22年の村名。直入郡三宅郷のうち。岡藩領。村高は「旧高旧領」の159石余のみ。文禄3年中川氏入部により,村の一部に竹田町が形成された。大野川と支流稲葉川の合流点に中世以来の岡城があり,ここに続く谷あいに武家屋敷や社寺が置かれ,向【むかい】丁・殿町・鷹匠【たかしよう】町・寺町・西裏町などの通称町名があった。向丁には中川氏の守護神天満社があった。殿町は上級藩士の居住区で,田能村竹田の住居竹田【ちくでん】荘があり,文政元年10月頼山陽が当荘に滞在。家老古田氏の屋敷もあり,近くにはキリシタン礼拝堂跡といわれる洞穴がある。寺町には寛永年中義祥の創建になる曹洞宗総持寺末豊音寺,寛文6年玉来【たまらい】町から浄土真宗東本願寺派光西寺(肥後八代城主相良義央の建立)が移築された。当寺は専超寺・西空寺・福田寺の塔頭をもつ。また寛文8年以来,士分以上の宿泊所の御客屋があった。寺町の寺院としてはほかに,寛永年中真言宗高野山派観音寺が建てられ,同11年藩主中川久盛の命により,境内に愛染堂と中国蘇州寒山寺を模した宗代楼閣様式を伝える月通閣が建立された。西裏町には慶長12年浄土宗知恩院派の正覚寺があり,八幡山には真言宗高野山派願成院(寺領20石)が元和4年に創建されている(地方温故集)。また同年中川久盛は京都愛宕社を城中北の尾に勧請,社領171石余・物成米61石余・大豆49石余を寄進(同前)。鷹匠町には藩校の由学館があったが,のち七里村に移転。天明7年医学校博済館が弥五兵坂に設けられたが,のち由学館に併合された。幕末当村内には,医師杉村白仏,僧田島喜惣,士分伊藤源兵衛らの開く8つの寺子屋があった。明治4年大分県に所属。同9年当時の村況は戸数626(うち士族558)・人数3,285,ほかに寄留者105。職業は農業50・猟師10・縫職10・養蚕8,産物は米20石・粟50石・大豆60石・小麦80石・繭9石・茶200斤,牛4(直入郡村誌)。同13年の戸数549・人口3,046。臼杵路・入田路・挾田路などの諸道が通り,稲荷谷・五右衛門谷・河内谷・地獄谷など谷の多い村である。同22年直入郡竹田町の大字竹田となる。

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7457320 |