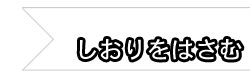東門(中世)


鎌倉期~戦国期に見える地名糠部【ぬかのぶ】郡のうち当地は糠部郡に置かれた東・西・南・北の門という四門制の1つである正安3年4月26日のきぬ女家族書上案に「八戸これかはの安藤三郎かめきぬをんなハ,ひかしのかとたね一のもくしきとう四郎にはつくたのめひ也」と見え,安藤三郎の妻きぬ女は東門種市の牧士きとう四郎の姪であった(新渡戸文書/岩手県中世文書上)糠部郡は鎌倉初期から北条氏得宗領となり,代官を派遣して所領管理にあたらせた東門の地頭代については未詳きとう四郎は東門の種市にある馬牧に働く牧士であった鎌倉幕府の滅亡により,糠部郡は没収されて足利尊氏に充行われ,北条氏代官の所領も没収されて,建武新政府側の人物に充行われることになった建武元年と推定される6月12日の北畠顕家書状に「久慈郡并東門事,当給人辞申候,仍未差遣代官歟,無沙汰之条,以外之次第也」と見え,久慈郡と東門は某に充行われたが,その給人がこれを辞退したため,代官を派遣していないことが知られる(遠野南部文書/岩手県中世文書上)元弘4年2月18日の北畠顕家国宣によれば,久慈郡は二階堂行朝に充行われたことが知られ(同前),東門も行朝に充行われたとも思われるが,詳細は不明永正年間の糠部九箇部馬焼印図に「右一箇部ノ七箇村宛合て六十三箇村也,此中に東西南北四門を立らる」と見える(古今要覧稿)一戸・二戸を南門,三戸・四戸・五戸を西門,八戸・九戸を東門,六戸・七戸を北門とする説(地名辞書)の根拠は乏しい東門は太平洋岸近くの岩手県九戸郡種市町・大野村に比定されている種市町と本県の三戸郡階上【はしかみ】町との境に角ノ浜【かどのはま】があるのは,東門の浜という地名の残存である階上町赤保内字寺下の観音堂にある寛保3年6月の奥州南部糠部順礼次第に「寺下東門一番正観音 脇士不動明王 毘沙門天王」とあり,順礼の打ちつけた御詠歌には「東門めぐりはじめの札うちて応物寺の下の観音」「東しかとめぐりはじめの名をとめて,おふもつ寺のしたのかんせおん」などとあり,この堂のある地は,東門の内であることをその頃も伝承していたことが知られる階上町も東門に含まれていたと思われる

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7252133 |