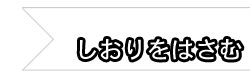藤懸(中世)


戦国期に見える地名越後国岩船郡小泉荘のうち永禄11年本庄氏の乱が起こり,大川氏の本拠であった当地は,本庄繁長・大宝寺義増の軍勢により攻略された永禄12年正月13日上杉輝虎は三瀦政長に大川長秀と相談のうえ「藤懸」への攻撃を命じている(米沢古案記録草案)同日大川長秀は藤懸の大宝寺勢を攻撃した(上杉家文書)本庄繁長は上杉氏の大軍に包囲され,伊達輝宗・蘆名盛氏を通じて和睦を乞うた上杉輝虎は繁長の長子顕長を人質として春日山城に在府させることで降伏を許した藤懸城も降伏し,同年4月19日の土佐林禅棟書状によれば,大川長秀は藤懸城に帰城した(上杉家文書)また,上杉輝虎から藤懸城攻撃に対する論功行賞として土佐林禅棟配下の土佐林時助に陣労を謝する直書(上杉家文書),土佐林能登守には段子1巻が与えられている(雞肋編/山形県史資料篇15上)現在の山形県東田川郡櫛引町三千刈字藤掛に比定する説があるが,誤り「慶長国絵図」に「藤懸り館」が見え,山北【さんぽく】町府屋の大川城にあたる

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7314623 |