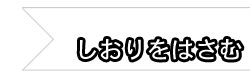衣裴荘(古代〜中世)


平安末期~戦国期に見える荘園名美濃国のうち治承4年5月11日付の皇嘉内院総処分状(平遺3913)に「みの うたのちよくし よひ ひはた」,元久元年4月23日付の九条兼実譲状(九条文書)に「美濃国宇多勅旨 衣裴 石田」とあるもと石田【いわた】とともに宇多勅旨【うだのちよくし】と称されて,皇嘉門院から九条家へ伝領された荘園だが,建長2年11月の九条道家譲状案・同初度総処分状では衣裴荘・石田荘とされ,宇多勅旨とは総称されていない(宮内庁書陵部所蔵九条家文書)当荘は建武3年以前に地頭との間に中分されていたが,その後さらに半済がなされたらしく,応永3年4月の九条経教遺誡では「美濃国衣裴庄半済内,半分御料所,半分秀阿御恩」とされているまた同人の同年12月の遺誡によれば,当荘年貢のうちより月宛100疋が4歳若君に,同1,000疋が堀川局に,同100疋が按察局に給されており,荘の4分の1が行孝入道の恩給とされていた以後,九条家の支配がいつまで続いたかは未詳天正13年5月14日,九条家雑掌は羽柴秀吉の京都奉行前田玄以に九条家領の指出目録を提出,そこでは不知行とされている(同上)翌天正14年には史料上に大衣裴・小衣裴両村が現れるが,それらは当荘内に成長してきた村落であっただろうなお,南北朝期には,土岐祐康(頼雄)が揖斐【いび】大興寺に寺領を寄進しているが,その1所として「衣裴大隴寺田畠」が見え,当時土岐揖斐氏の勢力が当荘にも浸透しつつあったことが知られる(大興寺文書・前田家所蔵文書)

 | KADOKAWA 「角川日本地名大辞典(旧地名編)」 JLogosID : 7343016 |