物納から金納へ――地租改正の目的は?

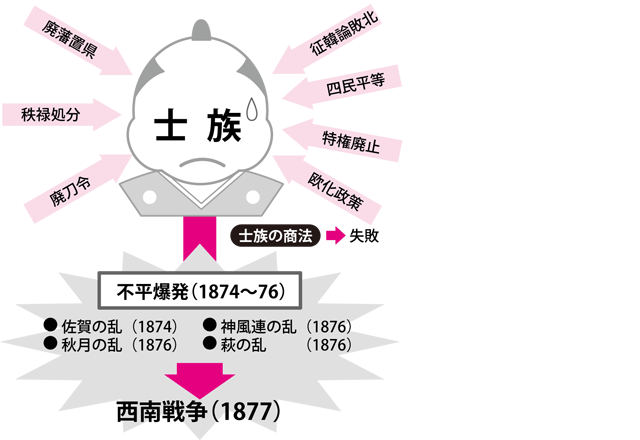
◎租税は年貢米から金納へ
江戸幕府の税収は、農民からの年貢がほとんどで、収穫の豊凶によって毎年の歳入が大きく変化した。この制度を、明治政府はそのまま引き継いだが、これでは毎年の予算を立てることがむずかしく、できるだけ早い時期に近代的税制を確立させなければならなかった。
1871年、廃藩置県が断行され、国家の中央集権化が一気に進んだ。これを機に政府は、税制と土地制度の改革に着手。同年、田畑でつくる作物の制限を撤廃し、年貢も米でなく貨幣で納めることを奨励。翌年には土地売買を許可し、年貢負担者を土地所有者と認定して地価を記した地券[ちけん]を発行した。土地は資本と化したのである。
ちなみに、地券発行のための土地調査で、所有権が不明確な入会地(村落の共有地)などは国有地に編入され、政府に大きな利益をあたえた。
こうした準備段階をへて、1873年、政府は地租[ちそ]改正を敢行する。地価の3%を地租(租税)とし、土地所有者に納入を義務づけたのだ。税率は収穫の豊凶にかかわらず一定とし、納入方法は金納とした。これにより、近代税制が確立され、国家の歳入は安定した。
◎農民は不満がいっぱい
だが、税の負担率は、かつての年貢と変わらず、かえって重くなった地方さえあった。政府は、将来的に地租を1%にすると約束したが、これまで黙認されていた隠し田にも課税された。
農民は新税制に強い不満をいだき、全国で地租改正反対一揆が頻発。とくに、1876年に発生した三重県や茨城県の一揆の規模は大きく、不平氏族の乱と結びつくことを恐れた政府は、地租を3%から2.5%に引き下げたのだった。
しかしいずれにしても、地租改正によって、国家の財政基盤は確立・安定したのである。

 | 日本実業出版社 「早わかり日本史」 JLogosID : 8539591 |



